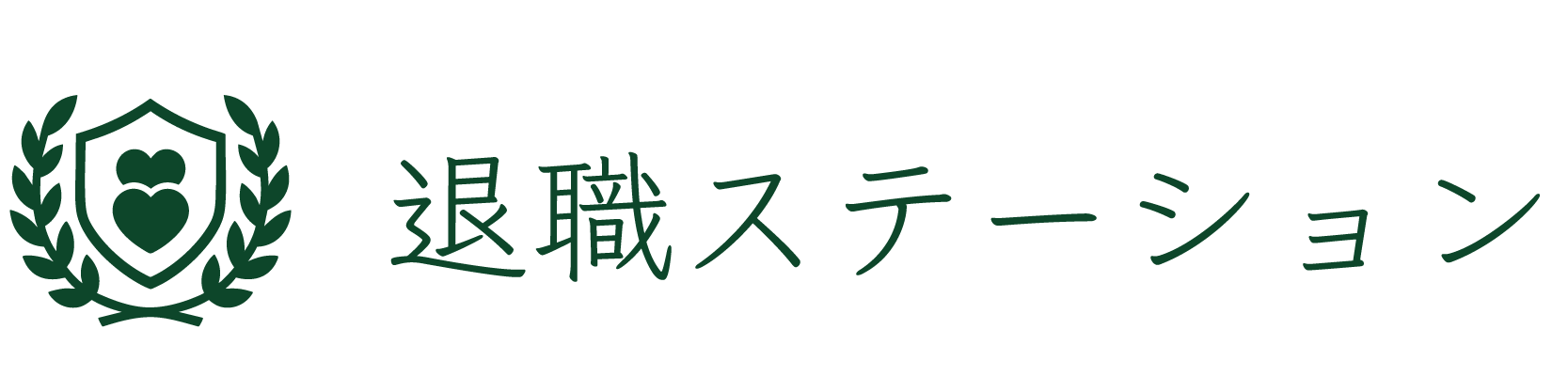退職すると「収入がなくなる」と考えがえられがちですが、実際には複数の給付制度が存在します。
代表的なのは、国の雇用保険制度による「失業手当」、健康保険制度による「傷病手当金」、そして会社が支払う「退職金」の3つが挙げられます。
これらの制度を正しく理解し、受給できる順番と組み合わせを把握することで、退職後の生活を安定させることができます。
本記事では、主要な給付制度の仕組み・金額・併用可否を比較し、「損をしない受給戦略」をわかりやすく解説します。
給付金制度の全体像|3つの制度の位置づけを整理
退職後にもらえる給付金は、前述した通り、大きく以下の3系統に分類できます。
| 制度系統 | 主な給付 | 管轄 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険制度 | 失業保険(失業手当)・再就職手当・教育訓練給付 | 厚生労働省 | 離職後に就職活動を行う人 |
| 健康保険制度 | 傷病手当金・出産手当金 | 協会けんぽ/健康保険組合 | 病気や出産で働けない人 |
| 企業独自制度 | 退職金・企業年金 | 会社(社内積立・外部共済) | 勤続年数のある退職者 |
制度によって管轄・申請先が異なるため、一括申請はできません。
主な給付制度一覧と特徴(早見表)
| 制度名 | 目的 | 支給主体 | 支給期間 | 支給額の目安 | 併用可否 |
|---|---|---|---|---|---|
| 失業保険(雇用保険の基本手当) | 再就職までの生活支援 | ハローワーク | 90〜330日 | 賃金日額の50〜80% | × ※傷病手当金と併罰用不可 |
| 傷病手当金 | 傷病手当金・出産手当金 | 協会けんぽ/健康保険組合 | 最長1年6か月 | 標準報酬日額の2/3 | × ※失業手当と併用不可 |
| 再就職手当 | 早期再就職を促す一時金 | ハローワーク | 一時金 | 失業保険の残日数×60〜70% | 〇 |
| 教育訓練給付 | 職業訓練・資格取得支援 | 厚生労働省 | 受講期間中 | 費用の20〜70% | 〇 |
| 退職金 | 勤続への報奨・生活支援 | 会社/共済/年金基金 | 一時金または年金 | 勤続年数・給与で算定 | ○ ※ 非課税枠あり |
雇用保険系の給付制度
雇用保険は、働ける状態で離職した人を支援する制度です。
中心は「失業保険(雇用保険の基本手当)」で、ほかにも再就職手当や教育訓練給付金などがあります。
就職可能な求職者が対象となる手当で、正式名称を「(雇用保険の)基本手当」と言います。
賃金日額(6ヵ月分のボーナス等を除いた給与を180日間で割った額)の50%~80%が90~360日間に渡って支給されます。
ガイド|受給条件・手続き・金額・期間を完全解説-520x300.png) 失業保険(失業手当)ガイド|受給条件・手続き・金額・期間を完全解説
失業保険(失業手当)ガイド|受給条件・手続き・金額・期間を完全解説
失業保険の受給日数が3分の1以上残っていた状態で再就職し、申請すると受給できる制度で、一時金として残日数で受給できる金額の60%~70%を受給できます。
 再就職・転職活動ガイド|退職後の仕事探しと再就職手当の活用法
再就職・転職活動ガイド|退職後の仕事探しと再就職手当の活用法
厚生労働省(ハローワーク)の指定する教育訓練(セミナーや講座等)を受講すると、受講費用の20%~70%を受給することができます。
健康保険系の給付制度
病気・けが・出産など「働けない」状態を支援する制度です。
中核は傷病手当金で、条件を満たせば退職後も継続的に受給できます。
なお、健康保険系の給付は、失業保険の”働ける状態であること”と排他的関係にあるため、同時に受給することはできません。
病気やけがなどで働けない状態であると認められた場合、標準報酬日額の2/3を通算1年6ヵ月受給することができます。
なお、受給には3日間連続で休んでいることなど、条件が細かく設定されています。
 傷病手当・病気退職ガイド|うつ病・適応障害等、病気で退職した人の給付制度を完全解説
傷病手当・病気退職ガイド|うつ病・適応障害等、病気で退職した人の給付制度を完全解説
出産のため休業した期間に受給可能な制度で、産前と産後で最大98日間(産前42日間+産後56日間)受給することが可能です。
退職時に労務不能かつ1年以上被保険者である場合、退職後も継続して給付金を受給することができます。
企業独自の制度
退職金など、企業が独自(法的な制度ではない)で設けている福利厚生制度も活用することができます。
代表的な制度としては、以下の3つの形態があります。
- 退職金制度(会社独自の規程に基づく支給)
※ 近年の中小・ベンチャー企業では、退職金を前払い(給与と合わせて)支給しているケースがあります。 - 中小企業退職金共済(中退共):
国が運営しているもので、中小企業が掛金を積み立てします。 - 確定拠出年金・企業年金:
企業・個人が積み立て、退職後に年金または一時金で受給します。(401k / DC等)
退職金は非課税枠が大きいのが特徴です。
例)退職所得控除:勤続20年以下=40万円×年数、20年以上=800万円+70万円×超過年数
併用できる・できない給付の関係一覧
| 組み合わせ | 併用可否 | 働けない理由 |
|---|---|---|
| 失業手当 × 傷病手当金 | × | 「働ける/働けない」の前提が矛盾 |
| 失業手当 × 再就職手当 | ○ | 再就職促進目的でセット給付 |
| 失業手当 × 教育訓練給付 | ○ | 職業訓練中も受給可(条件あり) |
| 傷病手当金 × 退職金 | ○ | 給与性・性格が異なる |
| 退職金 × 再就職手当 | ○ | 法律上の制限なし |
| 出産手当金 × 傷病手当金 | × | 同時期の労務不能に重複不可 |
制度を最大限活用する3つのステップ
雇用保険・健康保険ともに、被保険者期間が1年以上あるかを退職前に確認します。
自己都合 / 会社都合 / 病気退職によって給付開始時期が異なります。
企業独自の退職金等を受け取りつつ、病気退職なら「傷病手当金→失業保険」を活用し、通常の退職であれば「失業保険→再就職手当」のような活用が可能です。
よくある併用パターン別の解説
傷病手当金を申請し、療養後に失業保険(延長制度を含む)の申請を行うのがおすすめです。
すぐに失業保険の受給申請をし、求職活動を進めつつ、就職が決まったら再就職手当の申請を行うのがおすすめです。
出産前後で出産手当金を活用し、その後育児休業給付金を活用するのがおすすめです。
退職金を受け取りつつ、失業保険(ただし、65歳未満であること)を活用するのがおすすめです。
給付金の税金・社会保険上の扱い
| 給付金名 | 所得税・住民税 | 社会保険料 |
|---|---|---|
| 失業手当 | 非課税 | 保険料徴収なし |
| 傷病手当金 | 非課税 | 保険料徴収なし |
| 再就職手当 | 非課税 | 保険料徴収なし |
| 退職金 | 課税(退職所得控除あり) | 対象外 |
| 教育訓練給付 | 非課税 | 対象外 |
まとめ|制度を理解して“損しない退職”を実現
退職後の給付金は、制度を正しい順番で活用すれば最大限受け取ることができます。
同時受給禁止のルールを守りながら、「失業保険」「傷病手当金」「退職金」「再就職手当」「教育訓練給付」を正しく組み合わせ、経済的な空白を最小化していきましょう。
退職ステーションでは、あなたがどれくらいの退職給付金を受け取ることができるのかをLINEで無料で算出しています。
まずはご自身がいくら受給することができるのか、退職ステーションの公式LINEから確認してみてください。