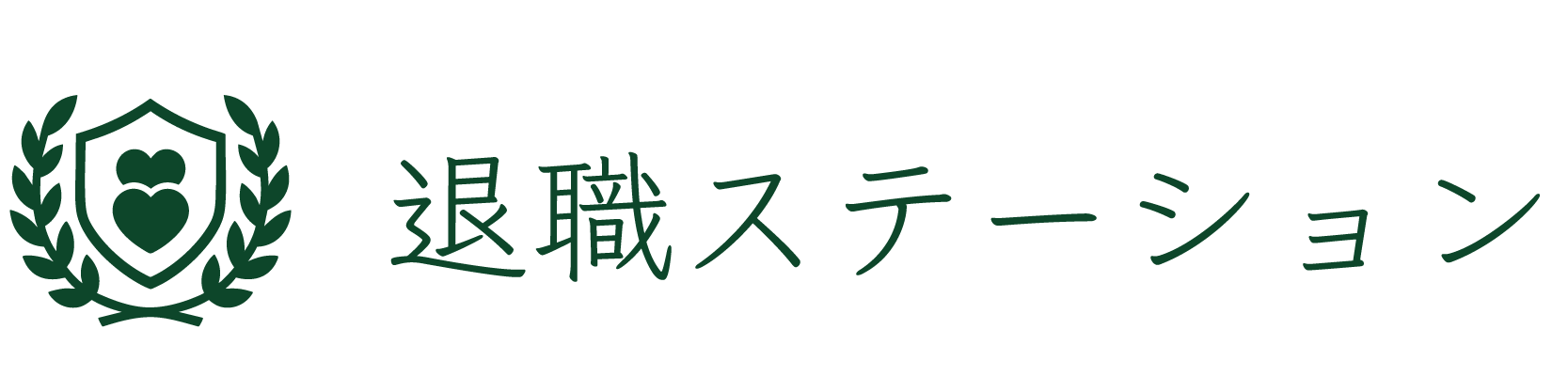うつ病や適応障害など、心の病気で休職・退職する人は年々増えている。
厚生労働省の調査(令和6年・労働安全衛生調査)によると、
「メンタル不調により連続1カ月以上休職・退職した人」は労働者の約10人に1人に上る。
うした場合、健康保険や雇用保険を活用すれば生活の支援を受けられる。
本記事では、
- 休職・退職時に使える給付制度
- 回復期の支援制度
- 復職・再就職の手順
を体系的に解説する。
メンタル不調で働けなくなったときに使える主な制度
退職や休職を検討する前に、以下の制度を確認しておくと安心できる。
| 制度名 | 管轄 | 支援内容 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 健康保険 | 給与の約2/3を最長1年6カ月支給 | 勤務中・退職後(条件あり) |
| 失業保険(基本手当) | 雇用保険 | 再就職支援・生活補助 | 回復後に働ける状態の人 |
| 自立支援医療制度 | 市区町村 | 医療費自己負担を1割に軽減 | 精神疾患の通院者 |
| 障害年金 | 日本年金機構 | 長期療養者への所得補填 | 長期・重度の症状者 |
| 就労移行支援 | 福祉サービス | 職業訓練・就職支援 | 就労準備段階の人 |
休職中に利用できる「傷病手当金」の活用法
- 医師による「労務不能」の診断がある
- 連続3日間の待期期間後、4日目から支給
- 給与が支払われていない(または減額)
傷病手当金(1日) = 標準報酬日額 × 2/3
標準報酬日額は、「標準報酬月額 ÷ 30」で求める。
例:標準報酬月額30万円 → 30万円 ÷ 30 = 1万円/日
→ 給付額:1万円 × 2/3 = 約6,667円/日
最長1年6カ月(540日)。再発・通算も可。
- 医師の診断書に「労務不能」の明記が必要。
- 精神科・心療内科の診断書も有効。
- 退職後も、退職前から受給していれば継続支給可能。
退職後に利用できる「失業保険」との切り替え方
傷病手当金を受け取っている間は、「働けない」とみなされるため失業保険の対象外。
就労可能な状態になった後に切り替え申請を行う。
- 医師から「就労可能」との診断を受ける
- 傷病手当金の支給終了
- 離職票・身分証を持参しハローワークで申請
- 雇用保険受給資格が決定
このとき、「特定理由離職者」(病気退職)として扱われる場合、給付制限が短縮される。
退職前にできるメンタルケアと相談先
- 産業医面談:勤務継続の可否を判断してもらう
- 人事部への相談:休職制度の申請手順を確認
- EAP(従業員支援プログラム):外部カウンセリング利用
| 窓口名 | 相談内容 | 運営 |
|---|---|---|
| 精神保健福祉センター | うつ病・適応障害・依存症の相談 | 都道府県 |
| 「こころの耳」 | 職場の人間関係・ストレス相談 | 厚生労働省 |
| 自立支援医療制度窓口 | 医療費軽減手続き | 市区町村 |
| 労働基準監督署 | 退職・休職トラブル | 厚生労働省 |
回復期に利用できるリワーク・社会復帰支援
復職や再就職を目的に、職場復帰準備を行うリハビリ訓練。
- 精神科・地域障害者職業センター・病院などで実施
- 集団活動や面談を通じて、ストレス耐性と生活リズムを再構築
- 医師・産業医・カウンセラーが連携して進行
復職・再就職に向けたステップと注意点
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| Step1 | 主治医の「復職可」診断を得る | 医療的判断が最優先 |
| Step2 | 産業医・上司と面談 | 勤務時間・業務内容を調整 |
| Step3 | 試験出社(リハビリ勤務) | 短時間勤務から開始 |
| Step4 | 正式復職または再就職活動へ | 無理せず段階的に |
- 復職後6カ月間は再発リスクが高いため、勤務条件を明文化しておく。
- 不調が再燃した場合、再度傷病手当金の申請が可能なケースもある。
まとめ|焦らず、制度を使いながら心身を回復させる
- メンタル不調でも、傷病手当金・失業保険・医療費助成制度で生活を支えられる。
- 無理に復職せず、「療養 → 支援利用 → 段階復帰」の流れが最も安全。
- 医師・支援機関と連携し、回復ペースに合わせて制度を活用することが重要。