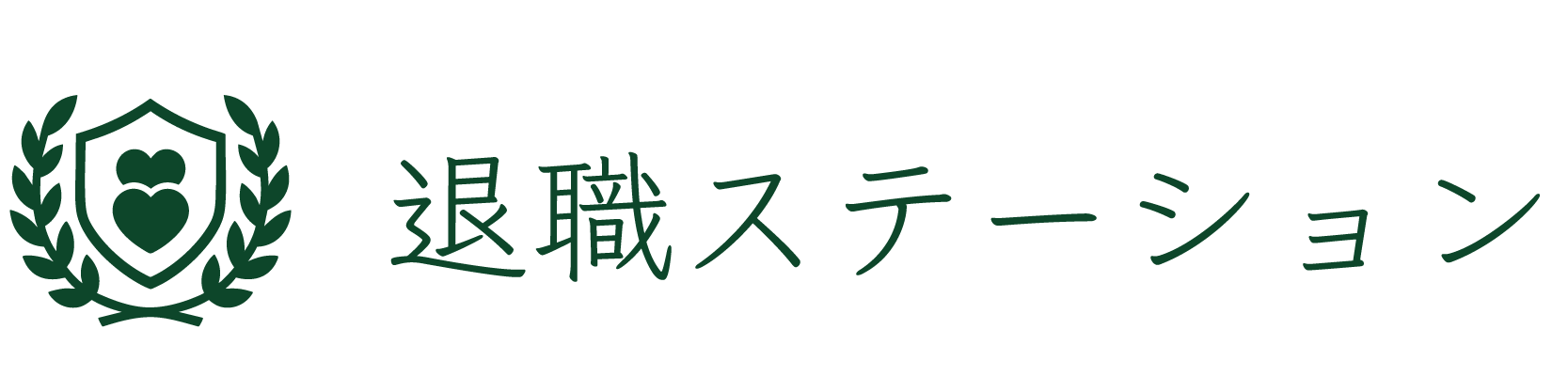退職給付金の代表的なものとしては失業保険(雇用保険の基本手当)が挙げられますが、失業保険は離職したすべての人が自動的にもらえるわけではありません。
受給資格は「離職理由」と「雇用保険の加入期間」で決まります。
自己都合・会社都合・病気退職では、給付開始時期や支給日数に大きな違いがあるため、まずは自分がどの区分に該当するかを正確に把握することが重要です。
失業保険の受給資格とは?基本ルールを確認
失業保険(基本手当)を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 雇用保険に加入していたこと
離職日から遡り、2年間の間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が通算12カ月以上あること。
(会社都合の場合は1年間に6カ月以上で可能)【雇用保険法第13条】 - 就職する意思と能力があること
就職できる健康状態で、求職活動を行っていること。(失業保険は働ける状態である必要がある。) - ハローワークで求職申込み・定期的な来所行っていること
申込みと同時に「受給資格決定」が行われ、指定された認定日にハローワークに出向き、求職活動の実績を報告する必要があります。 - 待期期間(7日間)を経過していること
求職申込みから7日間は、給付が行われない「待期期間」が設けられます。待機期間の間に働くことなく待機している必要があります。(その後、区分(自己都合退職等)により「給付制限期間」が追加される。)
これらを前提として、区分ごとの受給資格・条件の詳細を説明します。
自己都合退職の受給資格と注意点
「自分の意思で辞めた場合」は、自己都合退職として扱われます。
転職・家庭の事情・人間関係などが典型例だが、このケースでは失業保険の受給開始が遅れる点に注意が必要です。
前述の通り、自己都合退職の場合、離職前2年間で「雇用保険に12カ月以上加入していたこと」が必要です。
この“12カ月”は、単に在籍期間ではなく「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を指します。
- 求職申込み後、まず7日間の待期期間があります。
- さらに「自己都合退職」の場合は、給付制限期間が1カ月(2025年4月以降)設けられます。
- その後、最初の振込(退職から約1カ月半~2カ月後)が発生します。
失業保険は、基本手当日額(離職の日以前の6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額)と支給日数で決まります。
支給日数は、被保険者期間で次のように決まります。
| 被保険者期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
 退職給付金額ガイド|失業保険・傷病手当金はいくらもらえるか徹底解説
退職給付金額ガイド|失業保険・傷病手当金はいくらもらえるか徹底解説
離職票の理由が「自己都合」でも、実際の事情によっては優遇措置(特定理由離職者)を受けられる場合があります。
具体的には以下のケースなどが該当します。
- 体調悪化や家族介護による退職
- パワハラ・セクハラが原因
- 契約更新拒否で働けなくなった
これらは、「正当な理由のある退職」として扱われ、給付制限が免除される場合があります。
会社都合退職の受給資格と優遇内容
倒産や解雇など、会社側の事情で退職した人は「会社都合退職」に分類されます。
この区分は最も優遇され、給付開始が早く、支給日数も長いのが特徴です。
会社都合退職では、離職前1年間に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が通算6カ月以上あれば受給資格が得られる。
自己都合の12カ月より条件が緩い。
すぐに給付が始まる理由
会社都合の場合、給付制限がなく、待期7日が終わるとすぐに支給対象になる。
経済的影響を最小化する目的で、法的にも優遇されている(雇用保険法第22条)。
離職票の「離職理由コード」が誤っていると、会社都合なのに自己都合扱いになってしまいます。
例:解雇通知書をもらっているのに「自己都合」と記載されている。
その場合は、ハローワークで「異議申立て」を行い、証拠(解雇通知・就業記録など)を提出すれば訂正が可能です。
病気退職(特定理由離職者)の受給資格と手続き
うつ病・適応障害・がんなど、健康上の理由で働けなくなった場合は「病気退職(特定理由離職者)」に分類されます。
この区分は、会社都合と同様に給付制限なしで支給されるが、申請のタイミングと手続きに注意が必要だ。
- 離職前2年間に12カ月以上の被保険者期間
- 医師が「労務不能(働けない状態)」と判断していること
離職票の「離職理由コード」が33番または34番であれば、特定理由離職者扱いとなる。(離職理由一覧表)
病気退職時に「健康保険の傷病手当金」を受け取っている場合、失業保険と同時に受給することはできません。
傷病手当金の支給が終わってから失業保険の申請を行うのが正しい流れとなります。
 給付金制度比較・併用ガイド|失業保険・傷病手当金・退職金を徹底比較
給付金制度比較・併用ガイド|失業保険・傷病手当金・退職金を徹底比較
「診断書」だけではなく、就労不能期間と傷病名を明記した証明書が必要です。
これがないと、自己都合として処理される可能性があるため注意してください。
離職理由ごとの比較表
| 退職区分 | 給付制限 | 待機期間 | 必要加入期間 | 支給日数 | 延長制度 | 医師証明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己都合退職 | あり(1ヵ月間) | 7日 | 12ヵ月間 | 90日~150日 | × | 不要 |
| 会社都合退職 | なし | 6ヵ月間 | 90日~330日 | × | 不要 | |
| 病気退職(特定理由) | なし | 12ヵ月間 | 90日~360日 (回復後) | 〇(最大3年) | 必要 |
特定理由離職者と特定受給資格者の違い
| 分類 | 主な内容 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 倒産・解雇など会社側理由の離職 | なし |
| 特定理由離職者 | 正当な理由のある自己都合(病気・介護等) | なし |
両者とも給付制限なしで早期に支給が始まる。
よくある誤解と対処法
- 「退職届に自己都合と書くと不利」は誤り
→ 実態で判断される。 - 「延長申請は後からでも可」は誤り
→ 離職翌日から1年以内が期限。 - 「診断書があれば自動的に病気退職扱い」ではない
→ 労務不能の証明が条件。
受給資格を確実に得るための手続き
- 離職票-1・2を受け取る(会社から交付)
- 離職理由コードを確認
- ハローワークで求職申込み
- 受給資格決定通知を受領
- 病気退職の場合は受給期間延長を申請
- 認定日ごとに求職活動実績を報告
まとめ|退職理由を正確に伝えることが最大のポイント
- 給付条件は「離職理由」と「加入期間」で決まります。
- 会社都合・病気退職は待期7日のみで給付制限がありません。
- 自己都合退職でも「特定理由離職者」に該当すれば優遇されます。
- 離職票の内容が不正確だと支給が遅延する可能性があります。
正確な離職理由を伝え、必要書類をそろえて手続きすれば、失業保険を最短で受給することができます。
退職ステーションでは、退職給付金の申請から受給まで専門家がトータルサポートいたします。
まずはご自身が退職時にいくら受給することができるのか、退職ステーションの公式LINEから確認してみてください。