退職後の生活を支える制度として最も有名なのは「失業保険(失業手当)」ですが、もう一つの制度として利用可能な制度が、健康保険の「傷病手当金」です。
うつ病や適応障害、がん、慢性疾患など、病気で働けなくなったときに、給与の代わりとして生活を支える重要な給付制度です。
本記事では、病気やメンタル不調で退職した人が受け取れる「傷病手当金」についてわかりやすく整理します。
病気退職でも、制度を正しく使えば経済的に損をせずに療養・再就職準備ができます。
傷病手当とは|退職後も受け取れる健康保険の給付制度
前述の通り、退職した際に受け取れる公的給付金として、「失業保険(雇用保険の基本手当)」と「傷病手当金」がありますが、失業保険は「働ける」ことが前提であり、「傷病手当金」は「働けない」ことが前提であるため、両者は同時に受給することができません。
傷病手当と失業保険の主な違い
| 傷病手当金 | 失業保険 | |
|---|---|---|
| 目的 | 病気やけがで働けない期間、生活を保障 | 働く意と能力がある人が、再就職するまでの生活を保障 |
| 受給条件 | 病気やけがにより仕事ができない | 働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っている |
| 申請先 | 加入している健康保険組合や協会けんぽ | ハローワーク |
ガイド|受給条件・手続き・金額・期間を完全解説-520x300.png) 失業保険(失業手当)ガイド|受給条件・手続き・金額・期間を完全解説
失業保険(失業手当)ガイド|受給条件・手続き・金額・期間を完全解説
傷病手当金の窓口を担当しているのは被用者保険の保険団体ですが、代表的な全国健康保険協会(協会けんぽ)では、傷病手当金を以下のように定義しています。
傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために仕事に就くことができず、給与を受けられない場合に支給されます。
つまり、うつ病や適応障害など、病気によって働けなくなってしまった場合でも、給付金を受け取りながら療養する期間を設けられるということです。
| 保険の種類 | 傷病手当の対象 | 概要 |
|---|---|---|
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 対象 | 全国の中小企業で働く従業員などが加入 |
| 健康保険組合 | 対象 | 大企業や同業種の企業が共同で設立した組合に従業員が加入(関東ITソフトウェア健康組合など) |
| 共済組合 | 対象 | 公務員や私立学校教職員などが加入 |
| 国民健康保険 | 原則対象外 | 自営業者やフリーランス、年金生活者など加入 ※ ただし、一部の市区町村では独自の制度がある場合もあります。 |
| 健康保険の任意継続 | 対象外 | 退職後に健康保険を任意継続している期間は、傷病手当金は原則として支給されません。 ※ ただし、退職前に受給要件を満たし、継続して給付を受けている場合は、支給が継続されることがあります。 |
勤務先から保険証が発行されていれば、基本的には受給の対象となります。
傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガで療養中であること:
業務外の病気やけがで療養している必要があります。
業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。 - 労務不能であること:
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の判断によります。 - 4日間以上仕事を休んでいること
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を含める必要があります。
※ 4日目から支給の対象となります。 - 給与の支払いがないこと
休業中に会社から給与が支払われていない必要があります。
※ 働いており給与の一部が支給されているおり、その金額が傷病手当金より少ない際は差額が支給されることがあります。
傷病手当の申請の流れと必要書類
傷病手当金の申請は休職期間を設けた上で事業者と医師に記入欄への記載を依頼する必要があります。
- 所属の事業者(直属の上司等)に休職の旨を伝える
直属の上司の人など、所属している会社の人に働けない旨を伝えます。 - 傷病手当金申請書の記入
自身が加入している健康組合 / 協会けんぽなどから傷病手当金支給申請書をダウンロードし、本人(被保険者)記入欄に必要事項を記入します。 - 事業者・療養担当者欄の記入依頼
自身の所属している会社と通っている担当医に記入を依頼し、記載してもらいます。 - 傷病手当金申請書の提出
書類の準備が完了したら、その他の必要書類と一緒に、自身が加入している自身が加入している健康組合 / 協会けんぽなどに提出します。
申請後は、健康組合 / 協会けんぽなどの審査が行われた上で、不備がなく受給条件を満たしていれば、支給決定通知が届き、指定の口座に振り込まれます。
基本的には、上記の傷病手当金支給申請書のみ用意すれば問題ありませんが、ご自身の状況に応じて傷病手当金申請書の他にいくつかの添付書類が必要になるケースがあります。
申請書をダウンロードするページに状況に応じた必要書類が記載されておりますので、ご自身が加入している健康組合 / 協会けんぽなどのホームページを確認し、必要に応じて書類を用意してください。
傷病手当の給付金額
傷病手当金の給付金額は、1日あたりの金額と支給期間(通算)で決まります。
(支給開始日以前12ヵ月間の各月の標準月額報酬の平均)÷ 30日 × 2/3
- 標準報酬月額:
健康保険料や年金額の計算のもととなる、被保険者の月給を区切りのよい幅で区分した金額
支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合
以下のいずれか低い金額で計算します。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額
- 30万円(※):支給開始日が令和7年3月31日以前の方
- 32万円(※):支給開始日が令和7年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
傷病手当が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月間です。
通算であるため、仮に支給が開始された後に、一時的に出勤(給与が発生)し、再度傷病手当金の給付を再開した場合、出勤した期間は1年6ヵ月間には含まれず、その期間を除いた1年6ヵ月間分が支給されます。
※ 通算の考え方は2022年1月1日よりスタートしており、元々は支給開始日から最長で1年6ヵ月間でした。
なお、退職ステーションではLINEにて無料で給付金受給診断を提供しており、いくつかの質問に答えていただくだけで退職給付金を受給できるかどうか、またいくら受給できる可能性があるのかをすぐに確認することができます。
気になる方は以下のボタンより当社公式LINEに登録し、登録後の案内に従いご自身の受給可否を確認してみてください。
受給漏れ・損を防ぐための注意点
傷病手当金を受給するには、前述した4つの条件を満たすことを絶対条件として、審査を通過するために気を付けなければならないポイントがいくつかあります。
受給条件の1つとして紹介した「労務不能であること」を証明する医師の証明内容は気を付けなければならない要素の一つです。
担当医に「労務不能かどうか」を明確に記載してもらわなければ審査には通りません。
※ 診断書では代用ができないので注意してください。
傷病手当金申請書を記載してもらう際に気を付けなければならない点は以下の3つです。
- 労務不能と認めた期間:労務不能と認めた期間を過ぎてから記載していること
- 労務不能期間の明記:就労不能と認めた期間の最終日以降の日付が記載されていること
- 病名の一貫性:同一疾病で申請すること
※ 病名が変わると「別傷病」と扱われてしまい、審査が通りません。
自分の勤務先の健康組合 / 協会けんぽなどが申請書記入の注意点を掲載しているケースがほとんどですので、担当医に依頼する際は、申請書と合わせて記入を依頼することをおすすめします。
参考:全国健康保険協会 – 協会けんぽ – 「傷病手当金支給申請書の記入の注意点」
通院を途中でやめてしまうと「治療の意思が不十分」と判断され、審査が通らない可能性があります。
治療の意思を見せるためにも、月1,2回程度の通院をおすすめします。
傷病手当金の申請は、療養開始日から起算して2年間の間にする必要があります。
2年を過ぎると、時効によって給付金の受給ができなくなってしまうので、必ず2年以内に申請するようにしてください。
参考:全国健康保険協会 – 協会けんぽ – 「健康保険給付の申請期限について」
給付金を最大限活用するコツと併用戦略
病気で退職する際に給付金を最大限活用するには、「制度の順番」と「免除制度の併用」が重要となります。
- 退職前に医師と相談:
回復見込みと退職時期を確認。 - 傷病手当金で生活安定:
最大1年6か月間の傷病手当金を受給し、療養に集中。 - 失業手当への切り替え(再就職に向けた準備):
延長制度を活用すれば、療養後に受給可能となります。 - 社会保険料の負担軽減:
- 国民年金の免除や猶予申請が可能(日本年金機構 「国民年金保険料の免除制度・猶予制度」)
- 国民健康保険→所得減少による減免制度があります(市区町村窓口)
- 再就職
 給付金制度比較・併用ガイド|失業保険・傷病手当金・退職金を徹底比較
給付金制度比較・併用ガイド|失業保険・傷病手当金・退職金を徹底比較
よくある質問(Q&A)
医師の証明で「労務不能」と判断され、退職前に被保険者であれば受給可能です。
就職日以降は支給停止となります。再離職しても同じ病気では再支給できません。
退職後に発症・初診した場合は対象外となります。資格喪失時に「労務不能」でないと受給できません。
離職翌日から1年を過ぎると延長ができません。病気療養が長期になる場合は早めの手続きが必要です。
まとめ|病気退職でも傷病手当を活用して十分に休養可能
病気退職後は不安なことが多いと思いますが、傷病手当金を活用することで、退職後も安定した生活を送ることが可能です。
病気で体調が優れず仕事に支障をきたしている場合は、傷病手当金の活用を検討するとよいでしょう。
 メンタルケア・休職からの復職ガイド|心の不調と退職・給付金の活用法
メンタルケア・休職からの復職ガイド|心の不調と退職・給付金の活用法
ただ、これまで述べてきた通り、傷病手当金の申請は煩雑で申請するまでに時間がかかったり、病気で働けない状態であるにも関わらず審査が通らなかったケースなどが多々あります。
退職ステーションでは、これまで3,000名を越える申請サポートを行ってきた専門家が、お客様のご状況や今後のライフプランに合わせ、給付金を最大限受け取れるよう完全成果報酬制でご支援しています。
給付金に関するご相談やご自身が受給可能な給付金の算出など、退職ステーションの公式LINEで無料で提供しておりますので、お気軽にご連絡ください。
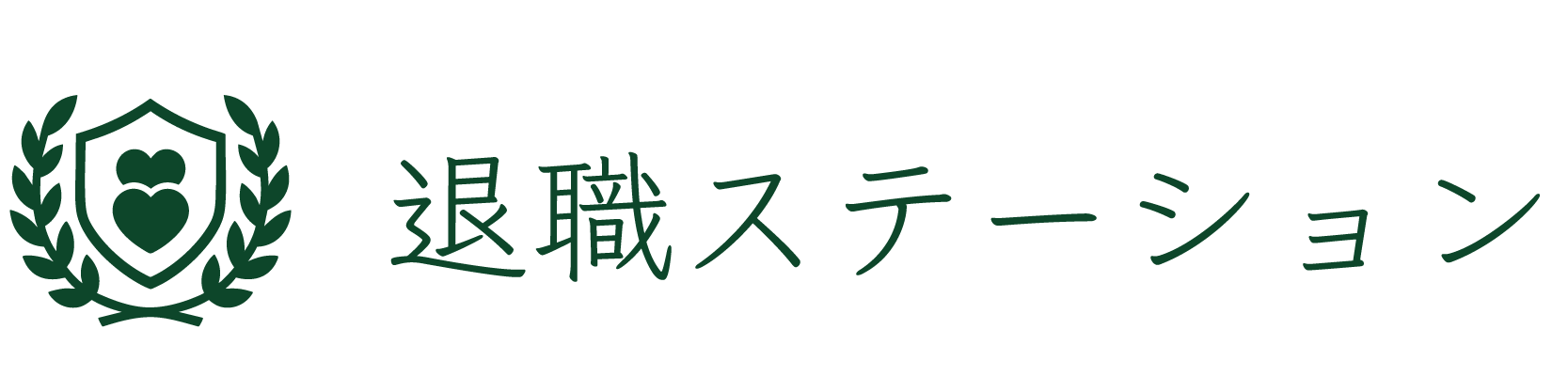

ガイド|受給条件・手続き・金額・期間を完全解説-160x160.png)
